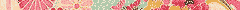長編集
□明告鳥
16ページ/45ページ
『竹林』
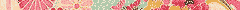
「殿内さん、江戸へ戻られるそうですね」
総司はにこやかに話しかけた。自分からこの人に話し掛けたのは初めてかもしれない。幕府からお目附を任されている殿内は、自然と派閥の長たる近藤や芹沢、もしくは土方や新見といった補佐的な役割を担う者と接触する事が多く、年若いと云うせいもあって、総司は碌に話した事も無かった。それでも、近藤や土方と話している時の言動や、それに応える二人の様子から、殿内が隠しているつもりでも滲み出る、見下したような態度には気付いていた。些細でもきっかけがあったなら、何か一言言っていたかもしれないがその機会も無く、まして二人が何の抗議もしない以上、総司も殿内に対して沈黙に徹するしか無かったのだ。
よく知りもしない人物にとやかく言うべきでない、常々そう自分に言い聞かせている総司が、嫌悪感を抱くに決定的だったのは、近藤と殿内が話している所に偶然通り掛った時だった。挨拶の途中、自分が免許皆伝であり試衛館の塾頭であると近藤から紹介された途端、ほんの僅かだが殿内の表情が歪んだのだ。頭の先から爪先までちらりと一瞥すると、軽く笑って会釈しただけでまるっきり別の話題を、総司を無視して始めた。
無言の侮蔑に苛立った。一言言ってやろうと身を乗り出した途端に手首をギュッと握られ、反射的に見上げた近藤が隣で引き攣った笑いを浮かべて堪えているのが目に入ってしまい曖昧な笑みでやり過ごした。嫌味の1つも言うならまだマシだったろう。
あれ以来何となく近付くのを避けてきた。若輩者なのは重々承知しているが、あの態度はやはり納得がいかなかった。芹沢のように芋道場だの田舎剣法だのとあからさまに言い立てる訳では無いし、面と向かって喧嘩を仕掛けてくる訳でも無い以上此方からは何も出来ず、仕方なしに努めて気にしないよう心掛けてきた。心の何処かに、近藤や土方が何とかしてくれるだろうと云う、他力本願な思いがあったのは否定出来ない。
しかし、今はもう違う。近藤が「頼んだぞ」と、笑いながら叩いた肩のその場所が、熱くなってくるのが分かる。浪士組として、将軍上洛の為都を警護すると云う当初の目的を果たす。その為に新な一派は必要ない。天然理心流を侮辱する者は許さない。土方の理論と近藤の想い、両方を背負っているのだと云う気概が総司にあった。中山道を旅しながら己に誓った事を、初めて成し遂げる機会だ。絶対にしくじらない、応えてみせる…、そう気合いを入れながら軽く会釈をした。